想像してみてください。
もし、何の音も聞こえず空気の流れもない、漆黒の闇の世界に突然放り出されてしまったとしたら、あなたはどうするでしょうか?
この暗闇の世界はどのくらい広いのか、どこに向かえば出られるのか、または出入り口があるのかどうかの判断材料もありません。
わかっていることは、悪い夢から覚めるようには元の世界に戻れないこと、そこに留まっているだけではいずれ死がやってくること、そして生き延びようとするならば自分の直感だけを頼りに、どこかに向かって進んでいく必要があることです。
ゾディアック最初の牡羊座から始まる12サインの長い旅路は、突如としてこんな暗闇に放り出されるように、何の準備も知識もなく、いまだ自分の身体感覚さえ掴めないなか、右も左もわからない世界でサバイヴすることから始まっていくと私は考えています。
そんなときに頼れるものがあるとすれば、それは「生きるんだ」という生命体のいちばん根源的な本能が引き出す、最大限に増幅された勘のようなものではないでしょうか。
「こっちに向かうんだ、きっと生きる道がある!」と本能の声を聞いたら、何の根拠もないただの思い込みであったとしても、全てを賭ける決め打ちのように、そこに向かって突き進んでいくしかないのです。
12サインが進むにつれ、私たちはこのもっとも根源的な本能の声を聞くより小市民的な型におさまることを選択したり、生に根差した衝動は抽象的な概念に比べて非文明的だとして一段低く見たりすることさえあります。
しかし、すべての始まりである燃えるような生への衝動は誰もが経験しているはずなので、意識的な社会生活の上ではそれを忘れてしまっていたとしても、命が尽きる瞬間まで心の奥底ではその火が消えることはありません。
それゆえに、本能的な生への希求があらゆる行動の源泉になっている牡羊座の姿は、平和な世界の中に生きている人々の魂にさえも響くのではないでしょうか。
そして牡羊座は、本能と同じく自分のうちに生まれた感情や衝動を躊躇なく表現することで、常識や習慣にとらわれスピード感をもって腰を上げることができない人々に先んじて、あらゆる時代や分野における先駆者となり得るのです。
今回はゴッホと草間彌生の作品を題材に、牡羊座が持つ生への希求と、衝動が切り開く新しい世界いうことについてお話ししてみたいと思います。
まずはゴッホの作品をいくつかご覧ください。



遠くから見ても一目でゴッホの作品とわかる厚塗りのタッチ、原色を組み合わせる色彩のコンビネーション。
私が足しげく美術館に通うようになる前から持っていた、ゴッホの作品に対する一貫した印象は、「うまいとは言えないかもしれないけど、この人の絵からは技術を超えた、ただならぬ気合いのようなものを感じる」ということです。
実際ゴッホは系統だった絵画の教育は受けていません。
画商見習いをクビになり、宣教師としても派遣元の教会から契約を打ち切られた27才の時、突如として画家になることを決意し、次のような思いを胸に、その後亡くなるまでの約10年間で2,000点以上の作品を描き上げます。
「絵は『意志と感情と情熱と愛』によって描かれるべきであり、『しばしば無意味な技術という言葉を、最近とみにもったいぶって使いたがる識者』の細かい詮索によって描かれるのではない。」
「ゴッホは彼を表現に駆り立てる衝動だけは、ありあまるほどもっていた。『僕の心と頭をいっぱいにしているものが、素描と絵に現れるに違いない。』」
(「ゴッホ 全油彩画 インゴ・F・ヴァルター ライナー・メッツガー」より)
先日もゴッホの作品を時系列的に30点ほど見る機会がありましたが、私が以前から持っていた「技術を超えた気合いのようなもの」という印象は、「絵画以外にはもう生きる道はない」という深いレベルでの決意と、人物を描こうが風景を描こうが、そのときの彼の心理状態や感情が生のまま投影されていることが理由ではないかと感じました。
たとえば、ゴッホが南仏の地アルルに芸術家のコミュニティーを築き、お互いに刺激し合いながら芸術性の向上を目指そうという希望に胸を膨らませていた頃の作品を見てみましょう。

花瓶に活けられた花や色調の明るさから、このときのゴッホには新しいチャレンジへの高揚感があり、招待した芸術家たちに対しておもてなしの心を持っていたようにも感じられます。
机の上の本が、エミール・ゾラの「生きる歓び」というのも、なんともわかりやすいところです。
次の作品はどうでしょうか。

これは、芸術家コミュニティーの計画がゴーギャン以外には無視をされ、そのゴーギャンとの共同生活もたった2か月で破綻してしまい、自分の耳を切り落とすなど精神に異常をきたすことが増え、長期の入院をしている間に描かれた作品です。
色調は明るいものの、木も草も山も空でさえも不規則にうごめくようで、見る者の心の内をざわつかせるところがあります。
ゴッホの弟のテオも、この頃の作品を見て、このようなことを言っています。
「兄さんの最近の絵を見て、それらを描いた時の兄さんの精神状態についていろいろなことを考えた。すべての絵に、これまでになかった色彩の力がある。それだけでも稀有なことだ。しかし、兄さんはもっと先まで行った。形態を力づくで変形させることによって象徴を求めようとする画家がいるとすれば、兄さんの絵の多くにそのような象徴が表現されているのを見いだす。(中略)しかし、兄さんはそのためにどれほど頭を使ったことだろう。なんとぎりぎりの限界まで突き進んだことだろう。そこまで行けば眩暈に襲われるのは無理もない。」
(「ゴッホ 全油彩画 インゴ・F・ヴァルター ライナー・メッツガー」より)
ここまで何点か見てきたとおり、ゴッホの作品は、鮮やかな筆致など外面の美しさにあふれているというわけではありません。
しかし、そのような美的な尺度を超えて、彼の絵画からは、自分の生そのものを感じ表現したいという魂の欲求が痛切に伝わってきて、人々は、いかに自らが人間としての初動的な衝動を包み隠しながら生きているかを省み、それを貫いた彼の作品や生き方に心を打たれるのです。
前出で近代のアートに関する多数の著作を持つ美術史家のインゴ・F・ヴァルター氏も、別の著書「フィンセント・ファン・ゴッホ」のなかで、画家の芸術的姿勢について、このように述べています。
「作品を作ることは彼にとって人生を描くこと、つまり単なる事実を描くのではなく、生命の原理を描くことを意味していた。」
また、ゴッホの時代までの西洋絵画と言えば、宗教画や肖像画、写実派、印象派あたりまでですが、どのタイプにしてみても様式が重んじられ、対象物をどのように描くのかということが主題で、彼のように自分の生そのものを描き切るという試みはなされてきませんでした。
そんなゴッホが西洋絵画にもたらした変革について、インゴ・F・ヴァルター氏は、ドラクロワの言葉を引用しながら、次のように語っています。
「ドラクロワも同じように考えた。『人間は古い軌道から脱するには、社会の幼児期に戻らなければならない。絶えざる変革が行き着く野蛮状態は、変化の必然的な結果である。』言うなれば、ゴッホはこの『野蛮状態』から出発する。」
(前出「ゴッホ 全油彩画 インゴ・F・ヴァルター ライナー・メッツガー」より)
ゴッホは、いわば様式を極めた古い西洋絵画の軌道から、画家としてのキャリア初期の試行錯誤を経て、当時としては極めて野蛮とも言える直接的な内面の吐露という作風に行き着いたといえます。
それゆえに彼の作品は生前には一枚しか売れなかったということは有名な話ですが、一人一人に固有な魂を描いて見せたことで、古い慣習に従うのみではない意志を持った個々の人間性の表れという、近代の芸術の扉を開いてみせたのです。
現在では世界中で最も有名な画家の一人であるのはもちろんのこと、彼が亡くなる数か月前には、メルキュール・ド・フランス誌で高い評価を得たり、展覧会ではゴッホの作品が最も素晴らしいとモネからも称賛されたり、早すぎる死がなければ、生前から時代の先駆者としてのふさわしい敬意を集めていたかもしれません。
自分の生きる道は絵画のみにあるという啓示的なコミットメントや、自分の感情や衝動をありのままに表現した作品の数々が近代芸術の先駆けとなったことを見ても、ゴッホの作品や生き方には、牡羊座の特徴をクリアに感じることができるでしょう。
次に、草間彌生の作品を見ていきましょう。



彼女の作品には、水玉や網、上の作品にもあるミジンコのようなものなど、極めて原始的なモチーフが使われています。
そしてそのモチーフも作品の中で何度も何度も繰り返されるという原始的な手法が取られ、作品自体も同じようなものが何度も繰り返し作られるという、作品にまつわるすべてのプロセスが呪術的で、何かに祈りをささげているようでもあります。
草間彌生本人は自伝「無限の網」の中で、幼いころから幻覚や幻聴を体験するようになった彼女にとって、精神科医の存在が今ほど一般的でなかった戦後すぐの時代、芸術だけが自分一人でそれらと闘う手段であったと語っています。
「人間だけが喋れると思っていたのに、私に言葉をもって交流してきたスミレたちに、まず私は驚いてしまった。その時、私にはスミレの花が人間の顔に見え、それが全部私のほうに向いている。私は恐怖で足がガタガタと震えるのをどうすることもできなかった。
私は走って走って夢中で家に逃げて帰った。ところが、途中から追いかけてきた我が家の犬が、人間の話す言葉で私に向かって吠えかかってきた。それに驚いていると、今度は私の声が犬声になってしまっている。(中略)
これらから逃れ得る唯一の方法は(中略)、それらは一体何だろうとかと、紙の上に鉛筆や絵の具で視覚的に再現したり、思い出しては描きとめ、コントロールすることであった。」
そんな彼女は、これぞ自分が生きる道と決意した芸術活動に限りない自由と広大なフロンティアを求め、国内で数回の個展を開いたのちに、海外への渡航を決意します。
とはいえ、まだ戦後10数年の1957年当時、米ドルの日本国外持ち出しですら制限があり、政治的や経済的に特別のコネクションを持たない人が国外に出ることさえかなり困難なことでした。
しかし、彼女の作品に特徴的な、内的イメージをそのままキャンバスに写していくような即時的なスタイルと同じく、渡航を思い立ったら、一面識もない当時すでにアメリカ画壇で地位を確立していたジョージア・オキーフに助力を求める手紙を出したり、違法に両替した米ドルを靴に詰め込んだりして、アメリカに渡ってしまいます。
そして、ニューヨークで大反響を呼んだのと同じシリーズの作品がこちらです。
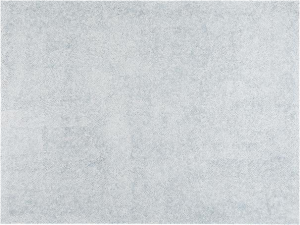
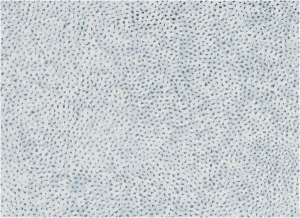
(出典 https://www.phillips.com/)
このシリーズの制作中、当時時代の寵児となっていたある画家は草間彌生に対し、こんな言葉を投げかけます。
「ヤヨイ、外を見ろ。ベートーヴェンやモーツアルトの音楽を聴きたくはないか。カントやヘーゲルを読め。偉大なものがいっぱいある。こんな無意味なことを、朝晩、数年もやっているなんて!時間の浪費だ。」(前出「無限の網」より)
しかし彼女には、水玉と網という内的世界のイメージをもって自分の生を実感し、芸術や人間そのものといういまだ未墾のスペースが限りなく残る荒野を、自らの感覚のみを頼りに切り開いてゆくという、あくなき欲求がありました。
「私には、一つ一つの水玉をネガティブにした網の目の一量子の集積をもって、果てしない宇宙への無限を自分の位置から予言し、量りたい願望があった。どのくらいの神秘の深さをこめて、無限は宇宙の彼方に無限であるか。それを感知することによって、一個の水玉である自分の生命を見たい。」(前出「無限の網」より)
ゴッホと同じく、草間彌生の作品にも、技術の細やかさや構造的な美があるわけではありません。
そこにあるのは、プリミティブなモチーフを無限に繰り返すという原初的な手法と、其れが醸し出す祈りのように切実な空気感であって、彼女の内的イメージを血がしたたるくらい原型のままにさらけだした創造物なのです。
過去数十年にわたって、草間彌生の作品は世界中いたるところの美術館から引っ張りだこですし、近年国際的に巡回している展覧会は各地で来場者数の記録を塗り替え、あまりの賑わいに24時間開場していたところもあったほどです。
もちろんカボチャや水玉模様のかわいさにポップアートの雰囲気もありますが、それはただ表面的に楽しいというわけではなく、彼女の芸術の源泉が本来人間だれもが持つ生命の熱源にあることを、人々が意識的に、または無意識的に感じているからこその人気なのではないかと私は考えています。
興味深いことに、草間彌生がゴッホについて評した言葉があります。
「たとえば、ゴッホの絵は何十億円もするからすごいとか、ゴッホは精神病で天才だからすぐれているとか、そんな考えをする人が世の中には多いが、そんなことではゴッホを観たことにはならない。(中略)
私のゴッホ観は、彼が病気であったにもかかわらず、その芸術がいかに人間性にあふれ、強靭な人間美を持ち、求道の姿勢に満ち溢れていたかという、その輝かしい美しさにある。その激越な生きざまにある。」(前出「無限の網」より)
彼女の言葉には、時代やスタイルは違っても自分の魂を描くことに人生の全てをつぎ込んでいる芸術家同士の共感があるように思えます。
画家になるまでのあらゆる仕事で挫折を味わったゴッホ。幼いころから現実と空想の混交に悩まされた草間彌生。
彼らは、自分の存在自体を脅かすほどの恐れを感じ、自分の内なる声に耳を澄ませました。「芸術しか自分の生きる道はないのだ」と。
魂の叫びと直結することで彼らの生のスイッチが入り、そこから出てくる感情や衝動、イメージもダイレクトに作品の世界に投影されていきます。
人間が持つ根源的な生への希求と衝動が切り開く新しい世界。それによってゴッホは近代芸術の扉を開き、草間彌生は前衛の女王として世界的なアイコンとなっています。
このふたりの芸術家からは共通して、牡羊座の才能が最高度に発揮されている姿を見て取れるのではないでしょうか。