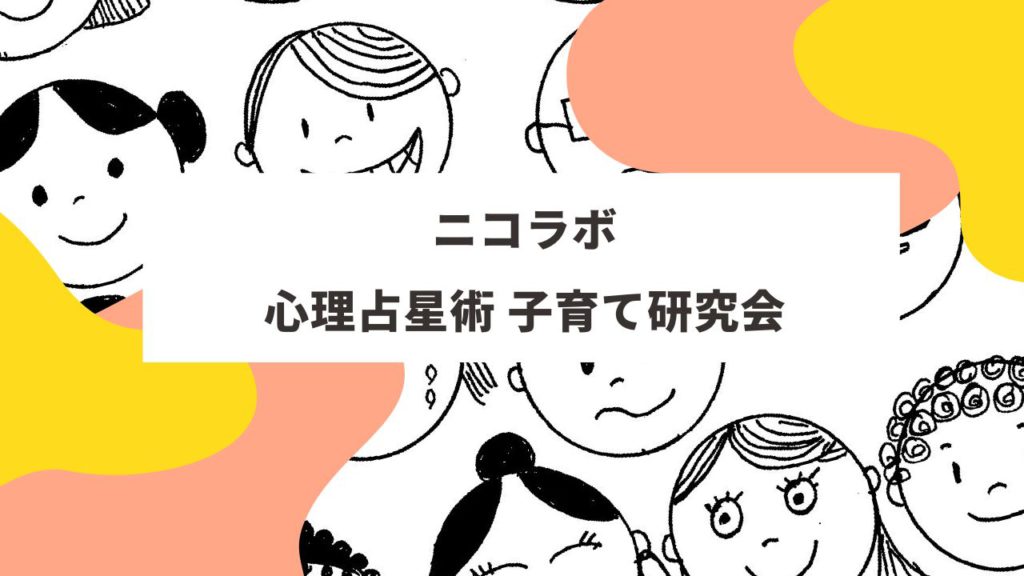
奇数月
第2金曜AM開催
2025年のはじまり
変化する時代の中、これからの子育てとは
2022年にスタートした子育て研究会。
この三年間、さまざまな子育てのお悩みについて、心理占星術的視点を用いて考えてきました。
当初は、お子さんの持つ資質と能力、抱えやすい葛藤をホロスコープ(特に個人天体)から分析し、大人ができるサポートを考えることからはじまりました。
そこから徐々にテーマが拡がり、家族の関係性についても扱うように発展。それぞれの問いに対し、心理占星術で見出せる範囲の提案を参加者全員で考えてきました。
・進路に悩むお子さんの未来の方向性や生き方を家族はどうサポートできるか
・兄弟姉妹や親子の不協和音。それぞれの力関係を分析し、家族内のコミュニケーションの調整はどうしたらよいのか
・引きこもりの子をもつお母さんの心配事、子どもと親の心理的ギャップ
・子育てを卒業した方の長年にわたる自信喪失に対するお悩みまで…。
そして迎えた2025年、子育てを取り巻く環境はますます大きな変化を迎えています。
AIの発展、社会構造の変化、価値観の多様化により、「正解のない子育て」がますます顕著になっています。そんな中、子どもの成長をどのように捉え、サポートしていけばよいのか。
こうした明確な答えのない問いに対し、心理占星術の視点は大きなヒントになりそうです。
そこで、これまでの心理学的な視点に加え、占星術らしい「時を見る」ことを加えた取り組みをスタートさせることになりました。
お母さんから見た「お子さんの転機」を取り上げ、その出来事は子どもたちにとってどのような意味があるのか。占星術の醍醐味でもある時期を読み解く三重円の技法を用い、お子さんの心象風景に迫ってみる意欲的な試みです。
さらに今回から、参加者のふーみんさんのご協力を得て、レポートをお届けしていきます。今後にご期待ください。
この記事を書いた人
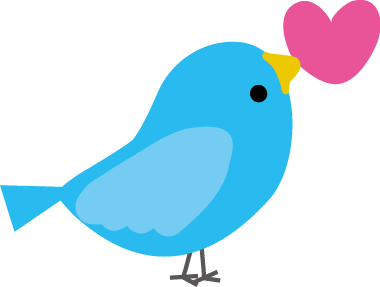
ふーみん さん
二児の母。2017年に火星サイクル手帳に出会い、心理占星術を学び始めました。子どもと共に成長する喜びを感じながら、心温まる子育てを実践しています。
ホロスコープから子どもの心は見えるのだろうか
心理占星術はさまざまな技法――出生ホロスコープやホラリーコンサルテーションチャート、三重円――を通して、その人が持っている生き方や考え方の癖、心の風景、欲望や衝動などを読み解くことを得意としています。
これまで研究会に参加し続け、いろいろな家族のお悩みを見聞きしてきました。
2025年最初の研究会では、新しい試みとして「その時、子どもは何を思っていたのか:時期を切り口に子どもの心象風景を考えてみよう」というお話がありました。
表現方法がまだまだ未熟な子どもたち、自閉症や障がいをもったお子さん、または反抗期でうまくコミュニケーションが取れていないなど、意志の疎通が難しいときに、出生ホロスコープ(ネイタルチャート)に語らせたら、もしかしたら子どもの欲望や衝動が見えてくるのではないか。
お母さんから見て、お子さんにとっての転機、大事だと思う瞬間、幾つかのタイミングを切りとったとき、子どものネイタルチャートにあるどの天体が使われて、何が引き出されたのか。
そこから成長のタイミングやその子がその瞬間をどう捉えているのかが分かることで、お母さんにとって励みや救いになることもあるのではないだろうか。
本当にチャートから子どもの声が読み取れるのか、使えるのかは分かりません。でも、この提案を聞いたとき、言葉にするのが難しい子どもの心を知る手掛かりになるかもしれないと思いました。
わたし自身、日々の関わりのなかで、「こんなふうに感じているのかな?」と想像しながら寄り添ったり、方向性を探ったりしていますが、自分の思い込みや決めつけが入り混じっているようで不安になるときがあります。
もちろん、チャートだけで子どもの心がすべて理解できるわけではないけれど、「ああ、もしかしたらこの子は、こんなふうに感じていたのかもしれない」と、腑に落ちることもあるのではないでしょうか。
nico 先生の提案は、『お母さんが「この子にとって大切な節目だったな」と感じる出来事を、その子はその瞬間をどう受け止めていたのか、どんな成長のきっかけになっていたのか』
この視点を取り入れることで、関わり方が変わることもあります。
「ああ、この子は今こんな流れのなかにいるんだな」
「この時期はちょっとゆっくり見守ってあげよう」
実際に、そんなふうに思えることがありました。
以前、娘がご近所でトラブルを起こして、この会でシェアをしたんです。かなりのやらかし案件だったので、母親として、戸惑い、落ち込んでいたのですが、nico先生の言葉は意外なものでした。
新しい世界に興味が向いてきて、そこに足を踏み入れたときに起きたインパクトのある出来事で、お子さんの世界が広がっている証かもしれません。
「まさか!そんなはずはない!!」と、最初は耳を疑いました。でも、チャートに表示された天体の象徴と、子どもの様子や出来事を語り直してみると、単なる問題ではなく、成長のプロセスとして見ることができるようになったのです。
この日は、さっそく参加者・MMさんのお子さんの時期についてチャート検証が行われ、ふーみんさんと同じような発見がありました。詳細は、別途ケーススタディとして掲載しますので、ご期待ください!
木星の成長――見える成長(射手座)、失望を伴う見えない成長(魚座)
この研究会では、定番となってきた「木星の成長」。
大事なテーマであり、繰り返し、取り上げられてきました。
木星は「成長」「拡大」「学び」の象徴とされ、子どもが新しい世界を広げていくプロセスを示します。しかし、心理占星術では、成長には「見える成長(陽)」と「見えない成長(陰)」の両面があると考えられています。
陽・射手座の木星は、「できる」ことが増える成長。
学校の勉強やスポーツ、習い事など、目に見える形で成長していくプロセスが、木星の「陽」の側面です。多くの親が望む成長です。(それだけが子どもの成長ではないことは分かっていますが…)
陰・魚座の木星は、「できない」ことの失望を受け止める心の器の成長。
nico 先生の心理占星術では、 この陰の成長を重要視しています。例えば、悔しい思いや失敗を経験し、それを乗り越えること。友人関係の中で葛藤を抱え、自分の感情と向き合うこと。こうした「見えない成長」こそが、長い目で見たときに大きな力となる。
表だって成長しているように見えなくても、実はたくさんの体験を通して、確実に成長している。そこを信頼することが木星の働きだと解説がありました。
目に見える成長をたくさん経験させたいと思う気持ちは、親としてとても自然なことです。
確かに、留学のような広い世界でたくさんの経験をすることは、子どもの成長にとって大きな助けになります。けれども、成長には、陽だけでなく、陰の経験もとても大切なものです。
「できないこと」「失敗すること」を受け止める力が育つ陰の場面では、親は子どもを信じて見守ること。ここは、親の忍耐が試されるところでもありますが。「親が先回りしてすべてを整えてしまうと、子どもが自分で成長する機会を奪ってしまう」という視点は、多くの親にとって気づきになるのではないでしょうか。
しかし、木星はある意味、厄介なようです。例えば、親の期待「こうした方が子どもにとっていい」という世間の常識といった、木星の「善きもの」に親自身が惑わされていると、判断がブレてしまう。
結局のところ、自分で子どもと向き合いながら、手探りで「善きもの」を見つけていくしかない。合っているかどうかはわからないけれど、「これがこの子にとっていいんじゃないか」と自分なりに思えるものがあるはずなのに、その一方で、「他の人から見たらどう思われるだろう」「何か言われるかもしれない」と、不安に駆られてしまう。
でも、そういう道のりを歩んでみるしかない。自分で歩んで悩みながら進んでいくしかない、というのが心理占星術的な木星の解釈でした。
タロットカードで木星に相応するカードは「隠者」。この絵が孤独であるように、本来、木星の世界は孤独な歩みだそうです。

そういう木星の世界を耐えきれなくて、指南書や啓発本をあてにしすぎたり、人の「いいね」に揺れてしまったりすると、木星のネガティブな体験を生んでしまうので注意が必要ですね。
現代の土星は変化している、ルールと責任を教える力
木星の「自由な成長」とは対照的に、土星は、「制限」「責任」「時間をかけて身につけるもの」を象徴します。これは、ルールや努力を通じて成熟していくプロセスですが、教育や子育てにおいては、子どもを縛り付けるような印象があるかもしれません。
かつては、「勉強しなさい」「良い大学へ行きなさい」「安定した職業に就きなさい」といった価値観が親の土星として機能していました。しかし、2025年の子育てにおいては、そうした「従来の常識」だけでは通用しなくなっています。
たとえば、大学の価値が変化し、「学歴より個性が重視される時代」になりつつあるようです。また、AIの発展により、今後求められるスキルや働き方も大きく変わるでしょう。
そんな中、親としてどのような「土星」を持てばよいのでしょうか?
「何を守り、何を手放すか」を決める
心理占星術では、土星を「本当に大切にしたい価値観」として捉えます。たとえば、「このルールだけは守るけれど、それ以外は自由にしていいよ」といった、親自身がブレない軸を持つことが大切そうです。
また、子どもが成長する過程で、子ども自身が自分なりのルールを作り、やり方を模索し、構築していくことをサポートするのも、親の土星としての役割として必要そうです。
nico 先生からはこんなお話がありました。
木星という社会の理想に対し、土星は一般常識や一般論。
今、わたしたちが持っている/知っている「社会の常識」は、本当にこれからの社会に必要なのかどうか。よくわからないところに立っていると思います。
これから時代が変わったとき、わたしたちの持っている常識は、もう違っているはずです。今を生きている子どもたちの方が、ずっと今の社会と接しているかもしれない。
そんな中、子どもにとって親が与えられる土星とは、何だろうか。
親の一般論や社会常識に頼るのではなく、むしろ、子どもたちとともに、親の方が(これからの社会常識を)一緒に学んでいく必要があるのではないでしょうか。
わたしの長女は、この春、支援学校の中学部を卒業しました。3年間で出来ること、やれることがたくさん増えました。本当にすごい。でも、親として一番うれしかったのは、先生やクラスメイトと信頼し合っている姿が見られたことでした。
小学4年生の次女は、学校での出来事をよく話すようになりました。「今のクラスが一番好きかも。はじめて終わっちゃうのが寂しいと思ったよ」と言っていました。
新学期、子どもたちはそれぞれ新しいステージでのチャレンジが始まります。
親としての不安がないわけではありませんが、親の不安から先回りしすぎず、子どもたちが自分で乗り越える機会を奪わないようにしたいです。たとえ、失敗やつまずきがあったとしても、それが成長の糧になると信じて見守ることだと知ったから。
そうはいっても、心配になるでしょう。そんなときは、まずは、深呼吸して「大丈夫、落ち着け」と自分に声をかけたいです。そして、子どもと一緒に成長していける親でありたい。
時代が大きく変わる中で、柔軟な心を持ちながら、子どもたちと一緒に新しい世界を見ていきたいと思います。
次回、開催予告
5/9(金)10:00~開催
詳細は近日発表
※どなたでもご参加いただけますので、お気軽にお問合せください。
ただし、zoom ライブ参加、お顔出しOKの方のみとなります。
☟こんな方におススメです☟
・子育ての悩みをシェアできる相手がいない
・子育てにホロスコープを活用したい
・お子さんとの相性が気になる
・お子さんのネガティブな面ばかり見てしまう
・お子さん、ご主人との関係性に悩みがある
・鑑定の現場で役立てたい方
・ホロスコープ読みを学んでいる方
・心理占星術を体験してみたい方
◆◆ 本研究会の特徴 ◆◆
参加者それぞれの立場から、子育てについての対話を重ねることによる気づきを大切にしています。
「お母さんは答えを求めているかもしれないけれど、「答え」を提示するのではなく、語ること(ナラティブ)の中で、自分の答えを選択できるような対話ができると一番いい」ーーこうしたnicoの所感から、今後もナラティブの積み重ねを行います。
偉い先生がお話しするのでもなく、占星術のチャートありきで学ぶのでもなく、ただ傾聴し合うわけでもない。人の話を聞きながら、自分の子育てを語り直していくことで、改めて自分を振り返ることができる。多様な考えを知ることは、閉じた子育てから解放してくれることもありそうです。
転勤族で周囲のママ友さんと深い話がしにくい、近くに両親など相談できる相手がいない、、、そんな方こそ是非ご参加を。お子さんの年齢やお住いの地域、バックグラウンドもさまざまな皆さんの声を聴くことで、きっと何かしらの発見があるはずです。
◆◆ 心理占星術子育て研究会について ◆◆
正解の見えない時代、答えのない人生に対し、 親や教育者たちは子供にどのようなことを伝えていくことができる のでしょうか。生きることを簡単に放棄できる時代に、 大人たちは子供たちに対し、 どんな生きる力を与えることができるでしょうか。
そもそも個性とは、その子らしさとは何を意味するのでしょう。
こうした問いに心理占星術のメソッドを応用、活用できないか。
参加者みんなで考えていく研究会です。
多くの方が抱えている子育ての悩みや不安はどこからきているのか 。
モヤモヤの原因は世間体や常識、既成概念にとらわれたもの、 占星術でいうところの社会天体(木星・土星)= 外発的なものなのか。
または、周囲の人や時代の影響によってあおらたもの、 占星術でいうところのトランスサタニアン(天王星、海王星、 冥王星)によるものなのか。
大人も子供も少しでも健やかに生きていくために、
また、これからの時代を生き抜いていくために、
心理占星術の考えや技術を利用し、 みんなで意見を出し合いながら、よりよい子育て、 親育ての方法を考えていきましょう。
一緒に情報収集やデータ分析などをしてくれる方、 自分の持っているリソースを共有し、 子供たちの未来を一緒に考えてくれる方のご参加をお待ちしています。